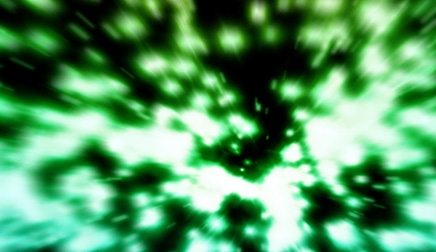Vol.02 安藤 孝浩
光の技術をつかって、フォトンと時間をアートにする

安藤 孝浩 Takahiro ANDO
プロフィール 1965年東京生まれ。1991年に東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻を卒業、教育研究助手を経て2012年まで東京藝術大学非常勤講師を務める。最近の作品に「ミッション[宇宙×芸術]−コスモロジーを超えて(東京)」、「川越灯りと音と文化の祭典(埼玉)」、「六本木アートナイト2013(東京)」、「バイオフォトン(韓国)」などがある。
記事掲載日:2015年10月6日
所属先・肩書その他の情報は当時のものです。
光の粒のひとつひとつを体感する。安藤孝浩さんは、そんな不思議な感覚をアートで表現した。実現の鍵となったのはPMT(光電子増倍管)(※1)。続く作品では、植物が発芽するときに発する微弱な光をとらえて、フォトンまたたく幻想的な世界を出現させた。光とアート、そのフロンティアを拓くアーティストの表現の行方にせまる。

フォトンのひとつひとつを音として聞く
光の信号を電子の信号に変え、増倍して取り出す「光電子増倍管」。その魅力にとりつかれて作品を作り上げたアーティストがいる。安藤孝浩さん。真っ暗な部屋に漏れこむわずかな光をとらえ、音に変換して聞かせる装置からは、光の粒のひとつひとつが、チリチリチリ……というノイズで伝わって来る。
「大学に入る前、デッサンの勉強をしていた頃から光に興味を持っていました」という安藤さん。絵を描くときに細部を克明に描写する方法ではなく、白・黒・グレーといった色面で光を描き分け、「近くで見ると描き込んでいないのに、遠くから見ると“すごいものを描いたな”」という絵の魅力にとりつかれた安藤さんは、光を使ったアートの表現にのめり込んでいく。
「あるとき、ファインマン(※2)という人の本を読んでいたら、PMT(光電子増倍管)をアンプとスピーカーにつなげたイラストが載っていたんです。この方法でやれば、光を音に変換して聞くことができる、と」。イラストを見ると、光を音に変換するのは簡単そうだった。だが、当時の安藤さんには技術的なことは全くわからない。いてもたってもいられなくなって、光電子増倍管を作っている会社をことごとく調べ、「ヒントが欲しい」と手紙を送った。
「すぐに返事をくれたのが浜松ホトニクスさんでした。僕がアートの世界で光電子増倍管に興味を持っていることに逆に興味を持っていただいて、『浜松に来ませんか』と誘っていただいたのです」。
安藤さんの願いは程なくかなった。訪問した浜松ホトニクスで安藤さんの構想は検証され、その設計図を持ち帰って自前で実験装置を製作。小型の光電子増倍管を組み込んだ装置を使って、光を音に変換してみた。ミニマムな光の粒が微かな音になって耳から飛び込み、視覚と聴覚が交錯する作品ができあがった。この作品はのちにCDにまとめられた。

“恐れ多い”気持ちを超えて挑んだ生物フォトン
安藤さんの光に対する興味はまだまだ続いた。「いろいろ考えて、次にとりかかろうとしたのが、植物の種が発芽するときに発するわずかな光=生物フォトンを使ったアートでした」と安藤さん。でも、構想を現実に移すには少しだけハードルがあった。それは「生物を相手にするのは恐れ多い」という感覚。「普通の光を機械で検出して作品にするのが家庭料理だとしたら、生物フォトンを相手にするのは高級食材を調理するようなもの。簡単に取り組んでいいものかどうかの迷いは大きかった」のだという。
「そんな感じでどうしようか悩んでいた頃、自宅近くの桜がきれいな川沿いを散歩していたとき、虫が左目に飛び込んできて、すごく痛い思いをしたんです。そのとき、ふっきれました。『これはやるべきだ』って(笑)」。

ちょうと同じタイミングで、メディア系のアートを紹介する美術館のキュレーターが、安藤さんの光のCDを聞いて興味を持ち、「新しい作品を作らないか」と打診をしてきた。思い切って「生物フォトンにチャレンジしたい」と言ったら、それで行こうとトントン拍子に話がまとまった。
出来上がったのは、生物フォトンをとらえて光電子増倍管で増幅し、ドーム型のモニターに内側から映し出すアート。ひっそりと息をひそめた生命が確かに生きていることを主張するかのように、光のドットが灯る。
安藤さんには、宇宙から地球を眺めた「お地球見」という作品もある。宇宙ステーションの窓に水を吹き付け、その水の面に映った地球を眺めるから「お地球見」。さかずきになみなみと注いだ酒に月を映して飲み干したりする万葉時代の日本のお月見文化と宇宙芸術とを掛け合わせて、その一瞬しか見られない風景を作品として楽しむ。
「お地球見」は、国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟で、文化・人文社会科学利用パイロットミッション(地球や宇宙に対する驚きや感動を芸術表現などを通じて発見することを目的とした実験)のひとつとしてChris Hadfield宇宙飛行士により実施された。

光と影がうねり、時間の流れを飲み込んでいく
光を扱うアートは時間の経過がもたらす偶然性の賜物、そう感じさせてくれる作品が他にもあった。山奥の別荘の縁側の窓に黒いビニルシートを吊って、内側から半田ごてで一個一個小さな穴を開け、射し込む光が外の風景を映し出すインスタレーション。
「僕のイメージでは、光の穴が増えるにつれて、外の風景がだんだん広がって部屋の中に入って来るというものでした。最終的にはビニルシートが星空みたいになるのですが、今見ている星は、何万光年も前の光が地球に到達して見えているもの。もしかしたら元の星は、今この時点では消えてなくなっているかもしれない。それと同じで、普段見ている風景も若干の時間的な距離があって、過去を見ているということになる。そんな、普段見ている風景との距離を伝えたいなと思ってやりました」。
星空のように穴が空いた黒いビニルシートの内側に、もう1枚、白くて薄い幕を垂らして風を送る。すると1個1個の穴がカメラのレンズのようになり、無数の反転した外の風景が白い幕に映し出されて波を打つ。ため息が漏れるような光と影のうねり。静かなのにダイナミックな景色のうえを、すべるように時間が流れていく。
現代美術に社会的なメッセージを込めるアーティストは多い。対して安藤さんの作品は純粋に光への興味から発しているらしい。「フォトン」という響きを聞くだけでゾクゾクするという安藤さん。次はどんな光のアートを思い描いているのだろう。
「光の技術を使ったものでは、フェムト秒(※3)という、ものすごい短い時間の変化が見られる装置を使って何か表現できないかと思っています。浜松ホトニクスさんでフェムト秒を計測できる装置を見せてもらって以来、光と時間の表現というのが絵にならないかというのが、ずっと頭にあります」。
この構想がどんなかたちを結ぶのか……そのサプライズが今から待ち遠しい。
※1 光電子増倍管
光のエネルギーを電気エネルギーに変換し、電流増幅することで微弱な光をとらえる高感度の光センサ。高速. 応答、超高感度などの特長があり、医用機器、分析機器、工業用計測機器などに幅広く用いられている。
※2 ファインマン
リチャード・P・ファインマンはアメリカ合衆国出身の物理学者。大学での講義内容をまとめた書籍『ファインマン物理学』は、世界中で愛読されている。
※3 フェムト秒
1フェムト秒は1000兆分の1秒のこと。