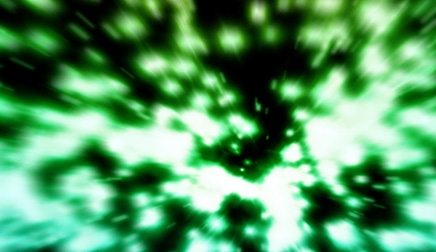Vol.06 村山 斉
私たちはどこから来たのか。科学の知恵を集めて謎に挑む。

村山 斉Hitoshi MURAYAMA
東京大学国際高等研究所
カブリ数物連携宇宙研究機構 主任研究者・教授・浜松プロフェッサー
プロフィール 1991年に東京大学理学部大学院物理学専攻博士課程を修了し、東北大学大学院理学研究科物理学科・助手、ローレンス・バークレー国立研究所・研究員、米国カリフォルニア大学バークレー校物理学科・助教授・准教授を経て、同大学物理学・MacAdams冠教授(現職)。2007年より2018年まで東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)初代機構長を兼務。その功績から2019年東京大学特別教授の称号を受ける。
記事掲載日:2020年3月30日
所属先・肩書その他の情報は当時のものです。
東京大学柏キャンパスにあるカブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU:Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe)。その起ち上げをした村山斉先生は、素粒子物理学者であり、すばる望遠鏡を用い最先端の科学で宇宙の謎に挑む研究チームの中心研究者でもある。アメリカと日本を行き来しつつ研究活動を進めながら、各地での講演をこなし、テレビ番組に出演したり、全国紙に記事を連載したりとその活動は多彩。宇宙の謎を解き明かすサイエンスの最前線と、バイタリティあふれるお人柄の背景を聞いた。
学校を休んで見たテレビ番組のインパクト
村山先生と接する多くの人は、気さくな人柄と豊富な知識、そして難しい科学の話を誰にでもわかるように説明してくれる技量に心底驚く。どんな半生を送ってこられたのだろうか。インタビューは子供の頃の話から始まった。
「小学生の頃は小児ぜんそくがひどくて、出席日数が危ないくらい学校をよく休んでいました。月に2回くらい副腎皮質ホルモンの点滴をして、満月様顔貌になるんじゃないかとか言われたぐらいですから、結構ひどかったんですよ」と村山先生は話し始めた。
ところがこの闘病生活が村山先生の才能を目覚めさせる最初のきっかけとなった。
「学校を休んで、昼間、家にいてもすることがないから、テレビをつけるじゃないですか。でも昼ドラを見てもおもしろくないわけですね、子供はね。だからしょうがないから、今で言うとEテレ、昔で言うと、NHK教育を覗いてみると、結構、おもしろい番組があったんです」
例えば、数学の番組では、高校の数学で出てくる「無限級数が収束する」という話が落語仕立てで説明されていたりする。
「ある人が、豆腐屋に豆腐を買いに行くんですが、豆腐を1丁買った後、『おやっさんの豆腐は、江戸一うまい!って、みんな言っているよ』 とおだて始める。そういうことを言い始めると、豆腐屋がいい気になって 『そうか、じゃあもう半丁くれてやるか』 と。すると今度は、『いや、だからホントにね、おやっさんは気前がいいんだよね。だから、みんな、この豆腐屋にくるんだよ!』と言うと、『そうか。じゃ、残りの半分もやるか!』と……」
まるで本当の落語家のように村山先生の話は続く。
「そうしているうちに、『もうわかった! わかった! 残りの半分! 残りの半分! 残りも全部くれてやる!』って言うんですよ。それを聞いて本人は、『これで一生、豆腐に困らない』と思うんですけど、ボールの中を見てみると、豆腐は2丁しかない。最初買った1丁と、次にもらった2丁目の半分と、その半分だから4分の1と、8分の1と……とずっと足していっても、2丁にしかならない」

ただ無限に数を足していっても、2にしかならない。「無限級数の収束」という一見難解な話が、豆腐に置き換えられてすっと頭に入ってきた。
「こんな事があるんだ!って、すごく興味を持ちました。その夜、帰ってきた父親に、こんなおもしろい番組を見たと言ったら、父親も研究者なので、『そうか』って言って、数学の本を買ってきてくれました。まずは中学の参考書を読み、次は高校の参考書。それも読んでしまったので、最終的には大学生が読むような本も読みましたね。」
小学生のころから大学生が読むような本まで読んでいたという村山先生。たまに行った学校では「しょっちゅう喧嘩していた」という。
「なんか許せないことがあるんですよ。クラスで一番のいじめっこがいて、何かカンに触ることをすると、本当に喧嘩するんですよ。家にいるときは病気だし、学校に行ったときは喧嘩して帰ってくるので、親にとっては大変な子供だっただろうなって(笑)」
科学の心を育てた父親の対応
その後、父親の転勤でドイツへ行くと、できたばかりの現地の日本人学校で、再び村山先生のキャラクターが発揮される。
「今でも覚えているのは、その日本人学校で、社会の先生が、何で春夏秋冬の四季があるかという話をした時のことです。地球の軸が傾いているから、夏は、東京がある北半球が日光をたくさん受ける。逆に冬は地球の位置が夏と反対になるから、南半球が太陽の方を向いていて、日光をいっぱい受けるんだという話を聞いて、“あっそうか、そうなっているんだ” と、子供ながらに非常に感動したんです」
そこで中学生の村山先生は社会の先生に質問をする。「先生、それだったら、赤道には年に2回夏があるんですね?」
地球の自転軸が傾いているために、日本の夏至の頃は、北極側が太陽の方を向き、冬至の頃は、南極側が太陽の方を向く。その中間の春分と秋分の頃は、赤道が真っ直ぐ太陽の方に向いているから「赤道には夏が2回あるはず」と言ったら、先生から返ってきたのは「そんな馬鹿な事があるわけないだろ!」。
「頭にきたんですよ。仕方ないから、学校の図書館に行って、世界各地の気温グラフとか見ると、たとえば赤道に近いケニアのナイロビなんかでは、きちんと年に2回、夏があるんです」
その本を先生のところに持っていって、「先生、赤道には2回夏がありますよね」と言ったところ、先生は黙ってしまった。何も言わない。「先生から見れば、面倒な子供だったと思いますよ」と村山先生。
「赤道には年に2回夏があるはず」という考えは、村山少年にとってみれば、「理論のある現象から紐解かれた新しい予言」だった。そして、その予言はデータで検証できるはずというのは、科学のプロセスそのものだった。そのプロセスに沿って図書館で調べたら、予言は的中した。つまり、赤道直下の夏問題は、科学のプロセスに沿って解決を見たことになる。
では、なぜ村山少年には科学のプロセスが実践できたのか。
「想像するにですね、子供の頃『これどうして?』とか『なんで、ああなっているの?』って好奇心だらけでいろいろ聞くと、父親も研究者だったので、ちゃんと答えてくれていたと思うんですよ。自分で答えられないときには、本を買ってきてくれたりしていました。」
そういう子供時代を過ごすと、一見不思議に見えることでもちゃんと理由があって説明できるという信念が芽生える。不思議なことがあれば、解き明かしたいと思う心が育つ。
小学生の頃の村山少年のように、多くの子供は、いろいろなことに疑問を持って大人に質問をする。でも時に大人は、時間のないことを理由にして、「そんな下らないこと考えてないで勉強しなさい」とか「先にご飯を食べなさい」とか「お風呂に行きなさい」とか言って子供の心を折ってしまう。
「そうすると、ディスカレッジされた子供は、そんな質問しても仕方がないとか、意味がないとか思ったり、質問しても答えはないかもしれないと諦めていると思うんです」と村山先生。続けて、「子供の頃からそういう質問に対して『そうだね、一緒に考えてみようか、調べてみようか』という親だったら、ずいぶん違うと思うんですけどね。」
言葉も文化も多様なのが当たり前
小学校5年生まで日本にいて、小6から中3までドイツの日本人学校に通うことになった村山先生。異国の生活はどんな風に映っただろうか。
「ドイツの生活はおもしろかったですね。もちろん環境が変わって健康になったから嬉しかったっていうのもあるのですが、それだけじゃなくて、ちょっと車で走ると違う国になるといった、日本では味わえないものがありました。」
村山一家が滞在していたドイツのデュッセルドルフは、オランダの国境近く。週末になると両親とともに車で2時間走ってオランダまで買い物に行った。当時はEUでもユーロでもなかったので、国が違うと物価も相当違い、オランダで野菜を買うとずいぶん安かった。
ドイツからオランダへと移動する道すがら、言葉も変化した。「ドイツとオランダの国境付近の言葉というのはドイツ語の方言で、ドイツ語からドイツ語の方言へ、そしてオランダ語へとだんだん変わっていくんです。」
例えば「おはようございます」はドイツ語で「グーテンモルゲン」だが、国境付近では「ユーテンモルゲン」になり、さらにオランダに入ると「フーデモルヘン」に変わる。「ありがとうございます」はドイツ語で「ダンケ」だが、オランダでは「ダンキュー」で、それが英語では「サンキュー」になる。
「だから言葉っていうのは、何語、何語ってきっちり分かれているんじゃなくて、つながっているんだっていう感覚がすごくおもしろかった。例えばお菓子屋さんでビスケットを買うと、その箱には小麦粉とか砂糖とかの主要成分が10か国語ぐらいで書いてあるんです。」
異なる国が地続きでつながっているというのもヨーロッパならではの特徴だ。いろいろな人がそれぞれの生き方で暮らし、つながっていて、それが当たり前という感覚は、日本では味わえない。ドイツで実感したことは村山先生のその後のキャリアに影響をしているようだ。
「外国に行くことにあまり抵抗がなくなるわけです。言葉が通じないとか文化が違うとかいうことにも抵抗がなくなって、何とかなるという風になってくるわけです」と村山先生は言う。
コントラバスを1日8時間も弾いていた大学時代

その後、中学3年生で帰国するが、中学の3年間を海外で暮らした経験は、日本の社会にある上下関係や言いたいことを口に出しにくい環境に居心地の悪さを感じる原因ともなった。帰国子女を受け入れる高校を経て大学に進学し、居心地の悪さはますます強くなっていった。
「高校は帰国子女ばかりですから文化は海外と同じ。だから大学に入って初めて日本社会に触れたんです。先輩には敬語を使わないといけないとか、カルチャーショックでした。それで、ろくに授業に行かなかった」と村山先生。
代わりに、なにか打ち込めるものが欲しいと思って、オーケストラに入り、1日に8時間もコントラバスを弾いていた。普通の音楽好きと違うのは、音楽もサイエンスの目で見、耳で聞いていたことだ。
例えば、クラリネットの音色とバイオリンの音色がなぜ違うか。
「高校のときから音楽が好きだったので、いろんな楽器の音色を録音して、その音の波の形をオシロスコープで見たことがあるんですよ。そうすると、バイオリンの波とクラリネットの波はこんなに違うんです」と村山先生はグラフを持ち出して説明する。

楽器の音の波形は、基本となる音に対して、2倍に早く振動する音、3倍に早く振動する音、4倍に早く振動する音…を全部足してできている。バイオリンの場合はそのすべてが足されて音になっているが、クラリネットの場合は偶数倍音が全部抜けている。それで何か抜けたような音が出る。
さらに、ドミソの和音がなぜハモるか。
「実は、これピタゴラスの発見なんです。決まった強さで張った弦を3つ並べて、ハモるところを探してみると、弦の長さがちょうど4対5対6っていう割合になったところなんです。これがドミソの和音です。」
宇宙は整数でできていると信じ、数でいろいろな現象を説明しようとしたピタゴラス。「ピタゴラスという人はちょっと神秘主義者で、ドミソの和音が簡単な整数の比率で美しく響くというのは、彼にとっては、すごく嬉しいことだった」と村山先生。
過去の偉人への関心が音楽への関心ともつながり、演奏の腕前もセミプロレベルだったという大学時代。都内の高校の入学式や卒業式に音大の学生と一緒に呼ばれて、演奏をしたこともあったという。
素粒子物理学との出会いと逆風
ところで村山先生は、専門の素粒子物理学とどこで出会ったのか。
「大学3年生のゼミで初めて素粒子物理の本を読んで、感激したんです。身の回りのものはすべて原子でできていて、原子には原子核があって、原子核には陽子と中性子があって、ということまでは高校で習って知っていました。でも、その中にはクォークがあって、そのクォークの間ではこういう力が働いていて、こういう性質があって、こういう粒子がこうやって発見されて…みたいな話は初めてで、それが、歴史読み物になっているような本だったんですよね。」
4年生の夏、大学院入試を受けるか音楽で食べていくか迷ったが、物事を突き詰めていくといろいろなことがわかる醍醐味を捨てられず、「突き詰める物理学なら、一番小さなものを扱う素粒子物理学」と決めて、大学院に進学した。
ところが再び逆風に襲われる。素粒子論の研究室に入ったが、誰も素粒子物理学の研究をしていなかったのだ。
「当時、その研究は時代遅れとされていました。先生に『こういうの、やりたいんです』と言うと、馬鹿にされるんですよね。『今頃なんでこんなことやるんだ』と。だから、研究室の中で完全に孤立していました。」
ある時、外部の講師を招いた集中講義が開催された。そこに、伝統的な素粒子物理学を研究する日本で数少ない研究者の一人が訪れ、村山先生の期待に応える講義をしてくれた。講義が終わるや先生のもとに駆け寄り、教えを乞う村山先生。答えは、「わかった。教えてやれなくはないけれども、自分はこれからイギリスに2年間行くことが決まっているので、帰ってきてからね」。
2年後、研究者の帰国を待って「教えてほしい」と再び頼み込むと、「教えてやると言ったのは覚えているけれど、一人だけに教えるのは効率が悪いから、少なくとも7人集めてください」と。
「全く人気のない分野だったので、7人を集めるために、広島大学に行って1人説得して、京都大学に行って2人説得して、東大の駒場キャンパスで1人説得して、後輩を2人説得してと、やっと7人集めた。それで合宿をやってもらいました」
これが、大学院博士課程2年目の3月のこと。ドクター論文はこの年の12月までに仕上げなければならない。4月から8ヶ月の勝負になった。
「その8ヶ月、むちゃくちゃ頑張りましたね。その時、初めてやりたい勉強ができた。頑張って、いろんな計算をして、ドクター論文を書いて提出した。そしたら、これが、落とされかかるんですよ。」
普通、ドクター論文の審査というと、最初は公開で行われ、途中から非公開になって審査員にいろいろ質問される。それが終わると、学生は退出し、審査員が議論を始める。普通は、ほぼすぐ合格が決まるので、外で待っていれば、5分もしないうちに主査が出て来て「おめでとうございます」となる。
「ところが、私は、部屋の外で待ってるんじゃなくて、『ちょっと研究室に戻ってろ』って言われたんです。研究室で待っていて、5分たっても、10分たっても、20分たっても誰も来ない。30分くらいたって、やっと主査じゃない先生が来てですね……」
村山先生のドクター論文は、素粒子の実験で反応を見る際、今まで計算できなかったような難しい反応も計算できるというソフトウェア開発に関わるものだった。実際にソフトウェアをつくり、計算機でいろいろなシミュレーションデータを出してまとめたものだが、実験の先生は「これは実験のデータではなく、ただの計算結果ではないか」と言い、理論の先生は「これ理論じゃないよね。単なるコンピュータのソフトだよね」と言って、審査会議は散々にもめた。
結局のところ「こういう計算ができないと、実験をやっても結果はわからないということになって、温情で通してくれたっていうことだったらしいのです。多分ボロボロだったんですよね」と村山先生。実はこのソフトウェア、その後、全世界で30年以上にわたって使われている。それほど価値あるものだったのだが、気づく人は多くなかった。
日本でやりたい研究が出来ない村山先生は、この数年後、アメリカ行きを決めた。
変な人がノーベル賞をとるバークレー
いろいろな人に相談してどこに行こうか考えた結果、UCバークレーを選んだ村山先生。その時のことを振り返ると「一気に陽が差したかのようでしたね」と笑う。
村山先生の目に映ったUCバークレーは例えばこんな感じだった。
「すごく変な人がいるんですよ。いろんな素粒子を発見してノーベル賞をとったルイス・ウォルター・アルヴァレズという伝説的な物理学者がいるんですね。彼のいちばん有名な論文は、『恐竜は隕石で死滅した』というものなんです。」
素粒子と恐竜、素人目には全く関係ないが、ルイス先生の頭の中ではつながっていた。
「素粒子の実験をやる人は、滅多に起きない反応をちゃんと見つけて調べるスキルがないといけないわけです。例えば、ごく少量の元素も、すごく感度良くつかまえる技術を持っています。」
ルイス先生は、ある時、メキシコのユカタン半島のそばにある地層で、イリジウムという元素が豊富な場所を見つけた。イリジウムという元素は、地球にはほとんど存在していないが、隕石に大量に含まれている。そこで、ルイス先生は「この地層は多分、隕石起源だろう」と考えた。
次に地層の年代を調べると、ちょうど恐竜が死滅した時代になる。「だから、この隕石が恐竜を絶滅させたんじゃないか」と、ルイス先生の頭の中でぱっとつながった。
村山先生は言う。「当時の古生物学者たちは、そんなこと考えていませんでした。だから、『物理学者が来て、変なことを言っているよ』というだけだったのです。でも今では定説ですよね。」

UCバークレーには日本では出会えないような自由な発想の持ち主がたくさんいた。自分の分野にこだわらず、「謎があるから解くんだ」「おもしろい問題に取り組むんだ」と、自分のスキルを全部使ってどんどん攻めていく、そんな文化が根付いていた。
「同じように、世界で初めてビッグバンの写真を撮ってノーベル賞を受賞したジョージ・スムートという人がいました。バークレーの同僚で、もともとは加速器を使って実験室でいろんな反応を研究していた人です。彼が、ある時、突然『自分は宇宙の始まりを知りたい』と言い始めたんです。それで周囲に掛け合って、望遠鏡を宇宙に向けて、撮っちゃった……(笑)」
突拍子もない人がたくさんいて、当たり前のように許容されている。それがUCバークレーだった。
「UCバークレーに行ってから、すごく楽しくなりました。『お前がやってることは時代遅れで、古い箱の中に入ってる人間だ』という位置付けで見られていたのが、『箱なんて関係ないんだ』っていう雰囲気に触れて、『とにかく自由にやっていいんだ』っていう解放感でいっぱいでしたね。」
素粒子と宇宙はどこでつながるか

バークレーのキャンパスを歩いていると、ノーベル賞受賞者のための駐車場が並んでいる。大学構内にも周辺にも一般の駐車場がない。「だから研究者は駐車場が欲しくてノーベル賞を目指すんです」とおもしろ半分に村山先生は言う。さらに素粒子の研究者でありながら、ビッグバンの写真を撮ってノーベル賞を受賞した同僚を間近に見て、「素粒子の研究と宇宙の研究は、つながっているんだ!」と実感することになる。
ところで、なぜ、素粒子の研究と宇宙の研究はつながっているのか。
「宇宙というのは観測できる最大のものですが、ビッグバンの写真に映っているごくわずかな“ゆらぎ”というかムラは、私たちが観測できる最小の素粒子に由来しています。素粒子は量子力学という不思議な法則に従います。量子的なふるまいというのは、毎回起きることが完全に予測できなくて、いつもちょっと不確定性があります。その不確定性が宇宙に焼き付いたのが、ビッグバンのムラなんです。」
素粒子の量子論的なゆらぎが、宇宙に種を作り、それが物質や生命の元になった。素粒子のようなごくごく小さな物質が宇宙の運命を決めていたことになる。
「宇宙が始まった直後に、インフレーションといって、ワーッと引き裂かれるように大きくなる時がありました。量子力学では毎回起きることが予測できないので、ワーッと大きくなっている宇宙のなかに、ちょっと濃いところと、ちょっと薄いところが生まれたんです。ちょっと濃いところにはダークマター※が多くて、その重力で周りのダークマターを引っ張ると、もっと濃くなって、もっと重力が強くなりますから、もっと引っ張って……と、濃いところがどんどん成長していって、それがいずれ、ぐしゃっと重力で潰れると星になって、銀河になって、我々も生まれたわけです。」
宇宙はインフレーションで始まり、ダークマターが物質や生命を育てた。
「だから、量子ゆらぎを作ったインフレーションが私たちのお父さんで宇宙に種をまいた。その種を育ててくれたダークマターがお母さんになって私たちが生まれたんです。そういうことなんです、宇宙って。」
※ダークマター:暗黒物質。質量は持つが光学的に直接観察できないとされていて、正体はまだわかっていない。
分野融合をするならテーマは宇宙だ!
2007年10月、数物連携宇宙研究機構(IPMU)設立(当時名称)と同時に初代機構長となった村山先生。だが、「機構長になるつもりなど毛頭なく、頼まれて企画書を書いていたら、たまたま機構長をやることになった」という。
当時、文部科学省が「世界トップレベルの研究水準」「融合領域の創出」「国際的な研究環境の実現」「研究組織の改革」を目標とした事業を打ち上げた。世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)だ。そこでUCバークレーにいた村山先生のところに、東京大学関係者が相談を持ちかけた。「理論物理や実験物理や数学や天文学の研究者を集めて、この構想に沿う新しい研究所を創りたい。どんな提案をすればよいだろうか」と。
村山先生の頭にはビッグバン後の宇宙のデコボコのイメージが浮かんだ。そしてひらめいた「新しい研究所のテーマは宇宙だ」と。
「この宇宙の中の、わずかなデコボコというのはある意味で音なわけですよ。空気の濃いところと薄いところを伝わってくるのが音で、これは宇宙に最初からあった音なんですよね。そういう音は元々、数学で説明できるし、その音がどうやって星になったかというのは物理だし、それを観測するのは天文だし……これでいきましょうという提案をしたんです。宇宙を軸に数学と天文と物理が連携する研究所だってことにしましょうって。」
ついでに「機構長もやってほしい」という依頼がついてきた。当時、村山先生42歳。研究所の予算は10年間で130億。
「40代の若造に国がそんな予算をつけることはないだろうと思ったんです。しかも日本で働いた経験もほとんどないわけですし。それに国は宇宙なんて実益のない分野にお金は使わないだろうとも思ったんですね」と村山先生。正直「どうせ落ちるだろう」と思って、提案書を書き、初代機構長として自分の名前を記して提出した。そうしたら、通ってしまった。
提案の可否を審査する審査員の3分の1が外国人で、推測するところ「日本を変えることが目的のプログラムだから、思い切って新しいことをやるところを通す」となったらしい。「おそらく外国人の審査員が、こういう変なのも1つくらい入れてやれって言ったのでは」と村山先生は笑う。
日本の研究者をもっと世界の舞台へ

Kavli IPMUの提案が通り、思ってもみなかったアメリカと日本の二重生活が始まった。「辛かったのは、自分のやりたい研究の時間がなくなっちゃったことです」と村山先生。他方、良いことも起こっていて、日本人の研究者を世界に紹介するきっかけともなった。
村山先生は言う。「ずっとアメリカにいましたから、日本人で良い研究をやっている人がたくさんいるにも関わらず、なぜか目に見えないっていう気持ちはずっとあったんです。」
英語力の問題や発信力の弱さがあって、おもしろい研究をしているのにアメリカで認められていない日本人の研究者は多い。「これはもったいない」という思いが永らくあったため、「Kavli IPMUを日本と外国をツーカーにする場所にしようと考えたんです。ある意味で出島ですよ」と村山先生。機構設立から10年以上たち、それは本当に現実になってきている。
分野融合を実践しているうちに、今まで良く知らなかった分野の研究内容を勉強することにもなり、思わぬ発見にもつながった。
「例えば銀河考古学って分野があるんですね。銀河の中の1個1個の星の運動を観測してその動きを逆算すると、実はこの星の群れは、最初はこの銀河ではなくて別の塊の中にいた。それが吸収合併されて、だんだん成長したんだ、ということがわかってきます。」
宇宙の遠くにある銀河は昔の銀河で、おしなべて小さくてイビツな形をしている。それが吸収合併を繰り返すうち徐々に大きく丸くなって綺麗な形になってくる。
「つまり、大人になって高齢化しているんですね。今の銀河は、ほとんど星を作っていません。今ある星は、ほとんどが全て100億年以上前に生まれた星で、今、実は本当に宇宙は少子高齢化しているんです。」
ところが高齢化した銀河同士が衝突をすると再び活性化されて、新たな星が数多く生まれるようになる。私たちの銀河も今から50億年後ぐらいにアンドロメダ銀河と衝突すると言われている。「そうすると多分、新しい星がたくさん生まれてきます。楽しみですよ、50億年後」と村山先生。
これが銀河考古学の世界だが、村山先生の専門である素粒子物理学とは全く異なる分野だ。ところが、そこで使われている手法が、先生自身が取り組む謎の解明に大きな役割を果たすことになる。
「実は銀河考古学では銀河の中の星の運動を詳しく調べますから、どのぐらいの重力で星同士が引っ張られているかがわかるんです。すると銀河の中にある目に見えないダークマターが、どこに、どれだけあるかがわかってきます。それをさらに調べていくと、ダークマターが互いに突き抜けるオバケみたいなものか、互いに時々ぶつかるような大きさを持ったものかという判定がつくことがわかってきました。それで銀河考古学を使って、ダークマターを調べようという新しい動きになってきたんです。」
これは分野融合の成果の一つと言える。Kavli IPMUでは毎日3時からティータイムがあって研究者は全員参加が原則になっている。シャイな日本人にはハードルが高い習慣だが、分野融合を成功させようと思えば、異なる分野の研究者同士がフランクに話をする場所は必須だ。
これからの目標、そしてフォトンとは
さて、一昨年、機構長の任を解かれた村山先生の現在の目標は何だろうか。
「今、一番集中して考えているのは、ダークマターの正体を知りたいということです。私たちのお母さんですから、会いたいじゃないですか。いろいろな調べる方法が出てきてやっているので、そろそろ捕まるんじゃないかなという感じはしているんですよね。」
さらにそのあとの目標は?
「宇宙の初めのインフレーションがまいた種をダークマターが育てたと言いましたけど、材料である原子がなかったら育てることができないんですよね。だけど宇宙が始まったときは原子もなかったし、物質ができたときには反物質と一緒にできているので、1対1で出来た物質と反物質は放っておくとまた消えてなくなってしまう。」
物質と反物質が打ち消し合って宇宙は空っぽになったはずなのに、なんで我々はここに存在しているのか。村山先生は続ける。
「物質と反物質ができたバランスを少しだけ崩して、ちょっとのズレで残ったのが我々だと思っています。では、どうやって、そのズレはできたのか。そこで期待されているのがニュートリノなんです。物質と反物質のズレが生まれた仕組みを重力波で調べようという研究も進んでいます。今まで全然関係ないと思っていたものが、もしかしたら、つながっているかもしれないという、そういう雰囲気なんですよね。」
謎を解こうとすると、素粒子と恐竜の関係のような、つながりが少しずつ見えてくる。それが果てしない好奇心を呼び覚ます。
最後にこのウェブサイトのテーマであり、素粒子の一つである「フォトン」について聞いてみた。素粒子の中で、フォトンって、どんなキャラなのですか?
「白くて小さなツブツブで、くるくる回っている、そんなイメージです。それがたくさんの情報を伝えてくれている。」
それは例えばどういう役割なのか。
「例えば何十億光年向こうの銀河があるじゃないですか。そこから出てくるフォトンというのは、四方八方に散らばるわけですよね。だけどその四方八方に散らばるフォトンが、なぜか、何十億年も走って、たまたまこの地球にやってくるわけですよね。ほとんどそれだけでも奇跡ですよね。」
「そのフォトンのおかげで遠くの銀河がどうなっているかわかるし、よく見ると実はいろんな色があるわけで、そのいろいろな色の仕組みっていうのを見てみると、どこに、どれだけ、どういう元素があるかとか、どういうふうに運動しているかもわかるんです。すごいいろんな情報を持ってきてくれるんです。」
フォトン(光子)は、村山先生の専門分野である素粒子の1つ※で、私たちにとってとても身近な「光」の正体。「電子」も素粒子の1つだ。私たち人間は、広大な宇宙の中、銀河系、太陽系の片隅に浮かぶ地球という惑星に「奇跡」的に生まれた存在。同じ宇宙のどこかから「奇跡」的に私たちのところにたどり着いた光や電子を利用して、地球の地面に張り付き、48億年の歴史を刻む一員となり、他の多様な生物とともに、生命感にあふれた星の生活を営んでいる…。ただ、それは宇宙についてのほんの少しだけの真実。フォトンや、それ以外の素粒子や、まだまだ分かっていないダークマターやダークエネルギー、さらには私たちの「心」だって、生まれた秘密やうまいこと働く仕組みがある。
「宇宙は数学という言語で書かれている」というガリレオ・ガリレイの言葉がKavli IPMUの交流広場にある柱(オベリスク)に刻まれている。「もっと世界のことを知りたい!」という思いが自然と浮かんだ。これがKavli IPMUの存在や、村山先生の活動から受け取るインスピレーションだ。
※素粒子は「標準理論」で以下の17種類が発見・予言されている。
自分たちの知らない世界があることを知ってほしい

目を輝かせて宇宙や科学を語る村山先生から、次の世代を担う子供たちに読んでほしい本を紹介してもらった。それは、ジョージ・ガモフの『トムキンスの冒険』。量子力学の世界をわかりやすい物語仕立てで伝えてくれる本だ。
「自分たちが知らない世界があるというのを知るのはいいんじゃないかと思うんですよね。SFじゃなくて、本当の世界で不思議なことがあるということを。」
私たちが当たり前のように使っているGPSも、相対性理論を使わないとまったく機能しない。便利さの背景にある科学へと子供たちの目を向けさせるのも大人の責任かもしれない。それは、「なぜ?」と問う子供の質問に面倒くさがらずに答えることとも通じる。
UCバークレーの学生たちにはよく「その問題がわかったときには、すでに半分解けている」という主旨の話をしているという村山先生。漠然と「わからない」ではなく、「ここがこういう風にわからない」と言えるようになれば、何をすべきかが見えてくる。それは、大人にも子供にも当てはまる問題解決の原則だ。
人生の早い時期に世界の広さと多様性を体感し、自身の才能を開花させる環境を選び取った村山先生。その言葉からは、日本の科学の発展と未来を担う子供たちの育成への、多様な示唆をくみ取ることができる。